家族が癌(がん)になったら必ず訪れる試練
こんにちは、婿殿ヒロです。
今回は少し重たい話をしますが、人生で多くの人が避けて通れない大切なことに触れます。
あなたは、家族ががんになったことはありますか?
私はこれまでの人生で、同居する家族のがんを4人も経験してきました。
がんと診断されると、その家族の人たちに必ず訪れる試練があります。
本人にがんを「告知」するのか、それともしないのか。
日本の医療制度においては、患者本人のへのがんの「告知」について、最終的には医師が判断するケースが多いです。
しかし一方で、医師が自分で判断せずに、「告知」の有無を家族へ委ねることも実は結構あります。
その代表的な例は、患者本人が85歳を超える【高齢者】の場合です。
実際、あなたも診察で告知するかどうかの判断を迫られたら、すぐに答えを出すのはそう簡単なことではありませんよね、、、
私は仕事で毎日がん患者(それも比較的末期がんが多い)に携わっているので、これまでに何千人もそういったケースを見てきましたが、いざ自分の家族となると全く話は別です。
妻も看護師なので、病棟などで私以上にそういったケースを経験していると思いますが、やはり自分の家族となると簡単に判断できませんでした。
この通り夫婦で長年がん医療に携わっていたとしても、家族へのがんの「告知」となると本当に悩まされてきました。
病院慣れしていない一般家庭であれば、なおさら、その判断は試練になるのではないでしょうか。
がんの「告知」の判断を、その家族に委ねる理由
それではなぜ、医師は「告知」の判断を家族に委ねるのか?
主な理由は以下の3つです。
① 患者本人の性格を知らない
がんの「告知」で一番辛い内容になるのが、がんの種類ではありません。
予後があとどのくらいなのか。
ドラマや映画などで馴染みのある表現を使うとすれば、本人への【余命宣告】。
「あなたは、○ヶ月後まで生きられる可能性は○%です。」
医師は様々な検査結果をもとに、統計学的なデータから具体的な余命日数を伝えますが、本人へ与える最もショックの大きい内容になります。
この厳しい話を何とか受け止められる人もいれば、全く受け止められない人もいるのが現実なのです。
その分かれ道になるのが、患者本人の性格。
つまり、毎日一緒に生活している家族が一番良く理解しているので、「告知」しても大丈夫な相手かどうかを家族に聞いているわけですね。
② 予後があまりにも短すぎる
患者本人ががんを受け止められる、受け止められない以前の問題で、そもそも予後が短すぎる場合があります。
具体的には、残り1〜3ヶ月の状況。
この予後になってくると、がんも相当進行しており、全身に転移しているケースが多いです。
いわゆる「末期がん」や「ターミナル」と呼ばれる段階ですね。
治療自体の選択肢も少なく、大半が「緩和ケア」といって痛みを和らげる治療や、なるべく苦しまないように最期を迎えてもらう治療方針へ。
予後があまりにも短すぎる場合、本人に告知すべきかどうかは最も難しい問題になります。
どんなにポジティブな性格だったとしても、受け止められるまでの日数が圧倒的に足りません、、、
周りのサポートなどが関わってくるので、医師だけの裁量ではどうにもなりませんから、やはり家族に告知の判断を委ねる形になることが多いです。
「本人には余命を伝えないでくれませんか?」
このように、がんであることは本人に伝えたとしても、短い余命については隠しておくケースも少なくありません。
「告知」に関わる最終的な話は、何が正しくて何が間違っているか誰にもわかりませんから。
③ 85歳を過ぎた高齢者
どんなに手術可能でも、化学療法や放射線治療などで効果が期待できる選択肢があったとしても、患者の年齢によっては何も実施できない場合があります。
特に85歳を超える高齢者においては、そもそも治療自体に身体が耐えられるかが重要になってきます。
言い方は悪いかもしれませんが、治療行為によって「止めを刺す」ことになりかねませんから。
これは一般の方にはあまり理解されないことなのですが、全ての治療には多かれ少なかれ必ずリスクが存在するのです。
85歳を超える高齢者にとっては治療行為自体が大きなリスクになり得るので、無治療(=何もせずに放置しておく)という選択肢も賢明な判断なのです。
医学で用いられる統計データというのは、あくまでも学問的に有意差があるかないかのデータなので、言い換えれば例外だらけ。
特に高齢者などはデータ自体に含まれないことも多く(本当です)、医師は結局のところ予想しか伝えられないのです。
完治を期待して積極的に治療することは、高齢者にとっては生死に関わるレベルで痛めつけられるということ。
無治療の選択肢によって、医師の予想を上回る寿命を全うした人たちは世の中に大勢います。
結局のところ、何も治療しないのであればそもそも本人に告知する必要があるのか?といった問題になりますから、あとは家族が判断して下さいということになります。
『告知しない』という選択肢、『無治療』という選択肢
社会的には「告知しない」という選択肢も、「無治療」という選択肢もまだまだ反感は多いのが実情。
しかし、それは外野の意見なので無視して下さい。
あなたが当事者になったら、よく考えて冷静に判断する必要があります。
残りの時間(予後)、治療の選択肢、そして本人の性格を併せて考え、最終的に「告知」すべきなのかどうかを判断するのが家族の試練なのです。
あまり議論されない内容ですが、今は2人に1人ががんになる時代なので、家族の誰かは必ずがんになります。
さらに、がんの発見率も年々上がっている。
これからの時代は「告知」や「無治療」への知識が必ず必要になってきます。
人生において必ず直面するであろうこの問題に、いざその時になってからでなく、普段から考えておくことが大切なのではないでしょうか。
最先端の医療行為だけが余命を伸ばす方法ではないということを、多くの人たちに理解してもらえれば幸いです。
最後に、がん治療のパイオニアとしても有名な近藤誠先生が執筆された書籍から、特に「余命」に関するものを紹介しておきますね。
私は偶然にも近藤先生と同じ放射線治療に携わる人間ですが、「余命」に対する考え方は目から鱗だと思えるほどでした。
読んだことがない方にはもちろんですが、がん医療の本質を知りたい方には特にオススメです!
がんが恐ろしいのではない。
「がんの治療」が恐ろしいのです。
歩いて病院に行ける人間が「余命3ヶ月」なんてありえません。
引用元:ベスト新書 近藤誠『「余命3ヶ月」のウソ』より
(絶対に読んでおくべきベストセラー↓)
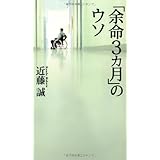 |
新品価格 |
 |
新品価格 |
 |
新品価格 |
 |
新品価格 |
あまり言いたくありませんが、がん治療の多くが病院の利益のためだったりします、、、
ここで紹介したどの本も医師の反感が多い(自分の仕事が減るので)のですが、近藤先生は医師の立場から事実を発信し続ける数少ない人格者です。
皆さんもぜひ、本当の「がん治療」を知って下さい。






